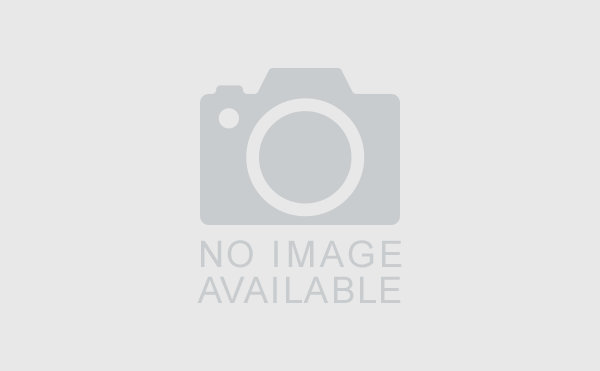美味い!アラカブの味噌汁
福岡生まれの知人男性が、長崎の奥さんの実家でアラカブの味噌汁を出された時「え~ 魚が入ってる… 」とお頭付きの魚がそのまま味噌汁に入っているビジュアルに驚いたそうである。男性は、これまで味噌汁の具は豆腐か、刻んだ野菜しか食してこなかったので、食べてみてその美味しさに驚いたのだとか。

アラカブとは九州での呼び名で、和名はカサゴである。岩場や海藻の多い海の底の方にいる魚で、防波堤からでも磯でも釣れる魚であるが、獲れる数が少なくスーパーではあまり見かけない。食すには骨が多く調理が面倒なため、内臓を出してそのまま煮付けや、味噌汁に入れたりする。
長崎の地方にある我が家でも夕食にはアラカブの味噌汁が頻繁に食卓に上っていた。実家を出てからは自分で作ることはないし、魚をメインにしている料理屋で頼むと結構な値段になるので注文するのを躊躇してしまう。幼い頃から、当たり前のように食べているものが、他の地域ではあまり食べられていないという事実に、大人になって気づいた食べ物のひとつだ。
私の地元に限ったことではないが、観光客を呼び込むのに「地方の魅力を発信」という言葉を見聞きするが、具体的にはどうすることを言っているのか?そもそも、地元に住む人は当たり前すぎて、魅力に気づいていないし、恥じてる場合すらある。
料理屋が「名物アラカブの味噌汁」とだけ宣伝したところで、観光客のどれだけの人が「食べたい、お店に行こう」となるだろうか?おそらく、食べた事のある近隣の住人が「あ~、いつも食べてるあれね」と一瞥して、通り過ぎるだけだろう。
食べた事のない人が、見慣れない魚が丸ごと入っている味噌汁を見て、どう思うだろうか?地方の魅力を発信しようにも、食文化の違う人達の目にどう映るかという想像力が欠けているように思う。
「食べたくはないが 義理の母が作った料理だから一口は食べないといけないかな?」など、他のプレッシャーを与えて、試食させるしかないか。