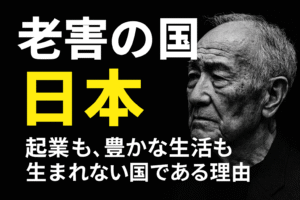引きこもりは“敗北”ではない──就職氷河期世代の再起と社会の責任
引きこもりの問題は、いまや個人や家庭の課題にとどまらず、社会全体の構造的な問題として表面化しつつあります。特に、現在40代後半から50代に差しかかる「就職氷河期世代」における引きこもりは、単なる“怠け”や“甘え”といった言葉では片づけられない、深い社会的背景を持っています。
就職氷河期という時代の重み
就職氷河期とは、1993年から2005年頃にかけて続いた長期不況の中で、企業の新卒採用が極端に絞られた時代を指します。この時期に高校や大学を卒業した人々、つまり1970年〜1983年頃に生まれた世代は、社会に出るタイミングでいきなり“椅子取りゲーム”のような過酷な競争にさらされました。
当時は、「いい大学に入って、いい会社に就職すれば安泰」という価値観がまだ根強く残っており、多くの若者が受験戦争を勝ち抜き、大学を卒業すれば未来は開けると信じていました。しかし、現実は非情でした。希望する職に就けなかった人、非正規雇用を転々とするしかなかった人、ようやく就職できても人間関係や職場環境に馴染めず、心をすり減らしていった人も少なくありません。
やがて彼らの一部は、社会との接点を失い、自宅の自室に引きこもるようになりました。これは、果たして「敗北」なのでしょうか?
「敗北」というレッテルの裏側にあるもの
たとえ、親や親戚、近所の人々が「就職できなかった=負け組」といった価値観を持っていたとしても、それが本当に正しいとは限りません。むしろ、当時の若者たちに必要だったのは、「レールを外れても生きていける」という別の選択肢を示すことだったのではないでしょうか。
生活のために別の仕事を模索する、自分で小さな事業を始める、あるいは思い切って海外に渡って働く。そうした発想や選択肢を、20歳そこそこの若者が自力で思いつくのは難しいものです。だからこそ、周囲の大人たちが「こういう道もあるよ」と助言し、背中を押してあげることができていれば、状況は少し違っていたのではないか。私は、そう思うのです。
外国人労働者に見る“生きる力”
一方で、私の近所のコンビニエンスストアでは、海外から来た就業者が流暢な日本語を話しながら、きびきびと働いています。人手不足の解決策として、外国人労働者の受け入れが進んでおり、その数は年々増加しています。
彼らは、異国の言語を習得し、文化の異なる日本で働くという大きなハードルを乗り越えてきた人たちです。その行動力と適応力には、ただただ感心させられます。
ふと、自分が同じ立場だったらどうだろうと考えてみました。もし私が海外のコンビニで働くとしたら、言葉の壁、渡航費用、不慣れな土地での生活……想像するだけで尻込みしてしまいます。果たして、自分にはそこまでの覚悟や動機があるだろうか、と自問せずにはいられません。
彼らの姿は、単なる労働力の補完ではなく、「働くこと」や「生きること」への強い意志とエネルギーの象徴のように感じられます。そして同時に、私たち自身がどれだけ恵まれた環境にいながら、その可能性を活かしきれているのかを、静かに問いかけてくるのです。
引きこもりと過疎化──構造的な視点からの仮説
「仕事があるのだから、引きこもっている人が外に出て働けば、過疎化や人手不足の問題は解決するのではないか?」
もちろん、現実はそう単純ではありません。引きこもりの背景には、精神的な問題や家庭環境、社会との関係性の断絶など、さまざまな事情が複雑に絡み合っています。誰もがすぐに外に出て働けるわけではないことは、十分に理解しています。
しかし、構造的な視点で考えてみると、興味深い仮説が浮かび上がります。
現在、日本には40歳以上で就業していない、いわゆる「中高年の引きこもり」が約74万人いるとされています。一方で、農業や漁業といった第一次産業では、就業者の平均年齢が約67歳と高齢化が進み、担い手不足が深刻です。
もし仮に、引きこもり状態にある人々の一部でも、適切な支援とマッチングのもとで第一次産業に関わることができたなら——。それは、社会的孤立の解消と地域の再生という、二つの課題を同時に解決する可能性を秘めているのではないでしょうか。
暴力的な“支援”と、見失われた尊厳
近年、いわゆる「子ども部屋」に引きこもる成人男性を、時に暴力的な手段で外に連れ出す専門業者の存在が報じられています。驚くべきことに、その依頼主は多くの場合、彼らの親です。
あるケースでは、見ず知らずの数人が突然自室に押し入り、ドアを破壊して本人を羽交い締めにし、無理やり部屋の外へ連れ出すという手法が取られているといいます。これは、もはや“最終手段”と呼ぶにふさわしい行為でしょう。しかし、私は思うのです。それが唯一の手段であるはずがないと。
人は、強制されて変わるものではありません。必要なのは、本人の意思を尊重しながら、社会と再びつながるための「小さな一歩」を支える環境です。
今という時代だからこそ、見える真実
日本では「終戦後」という言葉はよく使われますが、「敗戦後」という表現はほとんど耳にしません。これは、言葉の選び方ひとつで社会全体の認識が歪められてしまうことを示しています。
今という時代だからこそ、ようやく見えてきた真実があります。かつては「懸念」や「予想」として語られていたことが、今では明白な事実として私たちの目の前に現れているのです。
未来を切り拓くために
必要なのは、同情でも批判でもありません。現実的な支援と、未来への道筋を示すことです。就職支援、社会復帰の仕組み、そして「別の生き方があってもいい」という価値観の共有。それが、引きこもり問題の本質的な解決につながるのではないでしょうか。
たとえば、地域の中小企業や第一次産業と引きこもり当事者をつなぐマッチング支援、リモートワークやスモールビジネスの立ち上げを支援する仕組み、あるいは「働くこと」そのものの定義を見直すような社会的対話。こうした取り組みが、少しずつでも広がっていくことが求められています。
また、支援のあり方も「上から引っ張る」のではなく、「横に並んで歩く」ような姿勢が大切です。本人の尊厳を守りながら、社会との接点を少しずつ取り戻していく。そのためには、行政やNPO、地域社会、そして私たち一人ひとりの理解と関与が不可欠です。
終わりに──「問い」を持ち続けることの意味
引きこもり問題は、単なる個人の問題ではなく、社会の価値観や構造が生み出した“問い”でもあります。
- なぜ、あの時代に就職できなかった若者たちは、あれほどまでに追い詰められたのか?
- なぜ、異国から来た人々は、言葉も文化も違う日本で懸命に働けるのか?
- なぜ、私たちは「普通」や「常識」という言葉に、これほどまでに縛られてしまうのか?
これらの問いに、すぐに答えを出すことはできません。しかし、問いを持ち続けること自体が、社会を変える第一歩になると私は信じています。
今、私たちにできることは、過去を責めることでも、誰かを断罪することでもありません。むしろ、「これからどうするか」を一緒に考え、行動していくことです。
このエッセイが、引きこもり問題について少しでも考えるきっかけとなり、誰かの視点を広げる一助となれば、これ以上の喜びはありません。