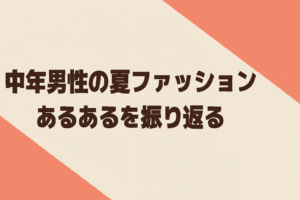関税戦争の行方──作る国、買う国の逆説
かつて「ものづくり」は国家の誇りだった。日本でもアメリカでも、町工場から世界へ羽ばたいた製品が数多く存在した。だが今、製造業は静かに姿を消しつつある。なぜか。その答えは、グローバル化と人件費格差の構造にある。
人件費10倍の壁
たとえば、日本国内で縫製業を営むとしよう。時給1000円で職人を雇い、丁寧に服を仕立てる。ところが、同じ服をベトナムで作れば、時給100円で済む。製品の完成度は同じでも、価格は10分の1。消費者は当然、安い方を選ぶ。これは小学生でも理解できる経済原理だ。
しかし、この単純な原理が社会に深刻な歪みをもたらす。国内の縫製業は価格競争に敗れ、廃業に追い込まれる。担い手は育たず、技術は失われる。農産物、加工食品、電化製品──ありとあらゆる「作る仕事」が、国民にとって「割に合わない仕事」となり、敬遠される。結果、製造部門は国内から消えていく。
「作る国」から「買う国」へ
この流れは日本だけでなく、アメリカでも顕著だ。かつて世界の工場だったアメリカは、今や中国から製品を買う「消費大国」となった。安価な中国製品がアメリカの市場を席巻し、国内の製造業は空洞化。トランプ政権はこの流れに歯止めをかけようと、関税政策を打ち出した。
2025年には「相互関税制度(Reciprocal Tariff)」を導入し、中国製品に最大50%の関税を課した。目的は明快だ。中国の言い値で買わされる未来を防ぎ、国内製造業を守ること。しかし、現実は複雑だった。関税によって部品や機械の調達コストが上がり、アメリカ企業の約33%が減益を見込む事態に陥った。製造業では42%が打撃を受け、復活どころかさらなる衰退を招いた。
会社に置き換えて考える
ここで、国家と製造業の関係を一つの会社に置き換えて考えてみよう。会社(=自国)は、製品を作るために従業員(=相手国)を時給で雇う。最初は誰でもできそうな単純作業を任せる。従業員は仕事を覚え、技術を身につける。やがて社長(=自国)は、自分では何もしなくても製品が完成し、売れるようになる。
この構図は一見、合理的だ。だが、従業員が技術を習得し、設計やデザインまで担えるようになったらどうなるか。社長はもはや必要ない。会社は、製品を「作る側」から「買う側」へと立場を変えざるを得なくなる。
これはまさに、アメリカが直面している現実だ。中国は製造だけでなく、設計・販売までを一貫して担えるようになりつつある。アメリカは、かつて自ら育てた「従業員」に依存する立場となり、価格決定権を失うリスクを抱えている。
トランプ関税は解決策か?
トランプ大統領が高い関税を課すことで、これまでの製造業流出の流れを止めて国内の製造業を復活させることはできるのだろうか。関税は一時的な価格調整にはなるが、根本的な競争力の回復にはつながらない。アメリカ連邦議会の一部はこの関税を「違法」とし、反発した。だが、彼らには製造業復活の妙案があるのだろうか。関税を否定するだけでは、空洞化した産業を再建する道筋は見えてこない。
アメリカ国民はこの関税をどう受け止めているのだろうか。個人で商品を買う立場からすれば、なぜ国が関税をかけて値段を釣り上げるのかと疑問に思うかもしれない。私自身、海外ブランドの服や車は特に生活に困らないから国内で買ったことはないし、別に生活に支障はない。海外ブランドの服やバッグは今も人気だが、高価になりすぎたこともあり、かつてのような関心を引く商品ではなくなった。
日本の現状と希望
日本でも、国産のカメラやテレビなどの電化製品、そして車も、サプライチェーンによって海外の優れたパーツを組み立てるだけの存在になりつつある。アメリカと同様に、製造の根幹が国外に依存している構造だ。
しかし一方で、国内でデザインされ、製造も国内でなされた服やプロダクトの一部には熱狂的な支持を集めるブランドもある。国産の農作物については、安心・安全で味も良いと海外でも人気が高い。これは「作る力」がまだ国内に残っている証でもある。
資本主義が生み出した労働の形として、投資家という存在がある。日本国内でも、株式投資によって数百億円を得た個人がいる。彼らは「買う力」を持つが、「作る力」は持たない。価値を生み出すのは、製造や設計、現場の技術者たちだ。
もしアメリカが価値を創造する力を失えば、どうなるのか。買うことはできても、作ることができない国は、いずれ他国の言い値でしか生きられなくなる。日本は「ものづくりの国」としての誇りを持ってきた。アメリカが辿った道を、日本が同じように歩まないことを願うばかりだ。
それでも、問い続ける
- 安く作ることは、本当に豊かさにつながるのか?
- 価格競争に敗れた技術や文化を、どう守るべきか?
- 「作る仕事」が敬遠される社会に、未来はあるのか?
- 投資だけで生きる社会は、持続可能なのか?
- 国産の価値を、どう再発見し、育てていくべきか?
このエッセイが、読者にとってその問いのきっかけとなれば幸いだ。